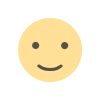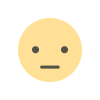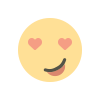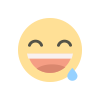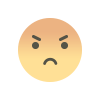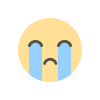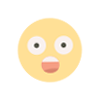原発30キロ圏の住宅耐震化率、8割全国平均下回る 屋内退避に懸念
全国15原発の周辺30キロ圏内の市町村の住宅の耐震化率を調べたところ、8割近くで全国平均を下回ることが分かった。これらの地域では、原発で事故があったときに、避難や屋内退避が求められるが、原発周辺の自治体で地震への備えが [...] The post 原発30キロ圏の住宅耐震化率、8割全国平均下回る 屋内退避に懸念 appeared first on Japan Today.

全国15原発の周辺30キロ圏内の市町村の住宅の耐震化率を調べたところ、8割近くで全国平均を下回ることが分かった。これらの地域では、原発で事故があったときに、避難や屋内退避が求められるが、原発周辺の自治体で地震への備えが遅れている実態が浮き彫りになった。

耐震化率は、震度6強~7でも倒壊しないとする「新耐震基準」を満たす住宅の割合をいう。全国平均は約87%(2018年時点)となっている。国土交通省が昨年11月に発表した各市町村のデータから、全基の廃炉が決まっている東京電力福島第一、第二原発を除く全国15原発周辺122市町村の耐震化率(算定時期は03~24年で、自治体ごとに異なる)を、朝日新聞が集計した。すると、95市町村で全国平均を下回った。
東京電力福島第一原発の事故を受けて原子力規制委員会が作成した「原子力災害対策指針」では、原子炉が冷やせないなど「全面緊急事態」になると、PAZ(5キロ圏内)の住民は30キロ圏外にすぐに避難し、UPZ(5~30キロ圏内)では一定の放射線量に上がるまで屋内退避をする。ただ、昨年1月の能登半島地震では、道路の寸断や建物の倒壊があり、地震と原発事故が重なった場合に、住民の避難や屋内退避の難しさが指摘された。
能登半島地震があった北陸電力志賀原発周辺では9市町のうち穴水町は48%、輪島市46%など8市町の耐震化率が全国平均未満だった。
耐震化率が最も低かったのは、四国電力伊方原発がある愛媛県伊方町の37.7%。九州電力玄海原発がある佐賀県玄海町は40.2%、昨年10月に再稼働した東北電力女川原発周辺は7市町のうち6市町が全国平均未満だった。
一方、南海トラフ地震が想定される静岡県は耐震化が進む。中部電力浜岡原発周辺では11市町が80%以上だった。
北海道余市町(北海道電力泊)、新潟県刈羽村(東電柏崎刈羽)、石川県志賀町(北陸電力志賀)、福井県池田町(日本原電敦賀)、美浜町(関西電力美浜など)の5町村は耐震化率を把握していないという。
ただ、耐震化率はあくまでも震度6強~7の1回の大きな地震に耐えられることを表す数字だ。2回目以降の大きな地震に耐えられる保証はない。原子力防災に詳しい関谷直也・東京大教授は「地震対策の一丁目一番地として耐震化は進めていく必要があるのと同時に、一般防災が不十分なことをふまえたうえで原子力防災を考えていかなければならない」と話す。
◇
国の原子力総合防災訓練が、14日から鹿児島県で始まる。訓練は16日まで。地震により九州電力川内原発1号機(薩摩川内市)が原子炉を冷やせなくなる全面緊急事態になる想定で実施。能登半島地震の被害をふまえ、道路が寸断し、孤立地区が発生する複合災害の対応を検証する。船舶やヘリコプターでの孤立地区の避難や物資の輸送、倒壊家屋からの救助、屋内退避、移動基地局を使った通信復旧などを行う。
記事後半では、原発ごとに周辺自治体の耐震化率の一覧をまとめています。
■能登半島地震で感じた「もし…
The post 原発30キロ圏の住宅耐震化率、8割全国平均下回る 屋内退避に懸念 appeared first on Japan Today.