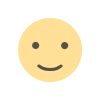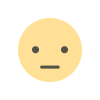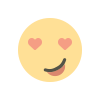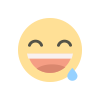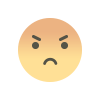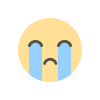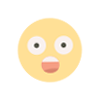受け継がれる神社の「どぶろく」 進む発酵、味に変化 中能登の恵み
天日陰比咩神社で醸造している「どぶろく」のふたを開ける禰宜の船木清崇さん=2025年1月27日、石川県中能登町二宮、砂山風磨撮影 日本酒の起源ともいわれる「どぶろく」。そんな素朴な酒とゆかりが深いのが、能登半島の付け根 [...] The post 受け継がれる神社の「どぶろく」 進む発酵、味に変化 中能登の恵み appeared first on Japan Today.


日本酒の起源ともいわれる「どぶろく」。そんな素朴な酒とゆかりが深いのが、能登半島の付け根近くにある石川県中能登町だ。全国に約8万ある神社のうち、醸造が認められている約30社中3社がこの地にある。
アルコールの甘い香りが、蔵いっぱいに広がる。天日陰(あめひかげ)比咩(ひめ)神社(石川県中能登町二宮)の境内にある「みくりや」には、木樽や陶器のかめが七つ並ぶ。禰宜(ねぎ)の船木清崇さん(51)がふたを開けると、神事用のどぶろくが顔をのぞかせた。
白く濁った酒の製法はシンプルだ。蒸し米と水、米こうじに酵母菌を加え、発酵させたらできあがる。とろみのある、まろやかな口当たり。これを濾(こ)すと、日本酒となる。
同神社では、江戸時代の藩政期には神事用に醸造されていたことが古文書からわかるという。豊作を祈願し、収穫に感謝して、神様に捧げてきた。明治時代には酒税の徴収のため自家醸造が禁止されたが、いまも税務署長の許可を得て伝統を受け継ぐ。
使うのは、町内で収穫された奉納米と地元のわき水だ。10月下旬に醸造を始め、みくりやで2週間から1カ月発酵させて完成する。近年は約500リットルをつくり、初めて神様にお供えするのは、12月5日の新嘗(にいなめ)祭だ。地域では「どぶろく祭り」と呼ばれ、お神酒(みき)として振る舞われる。
酵母菌に秘密 「一期一会を楽しんで」
船木さんは、千差万別の味が魅力の一つという。その年の気温や奉納米の性質によって味は変わる。神社によっても異なるという。日本酒は火入れして発酵を止め、味の変化を防ぐ一方、どぶろくは火入れをしないため時期によっても味が変わっていく。12月にはぴりっと、2月にはまろやかに。参拝後には、お祓(はら)いとして飲むことができ、「味の変化を楽しむ氏子(うじこ)さんも多いです」と船木さんは話す。
さらに同神社では、石川県立…
The post 受け継がれる神社の「どぶろく」 進む発酵、味に変化 中能登の恵み appeared first on Japan Today.